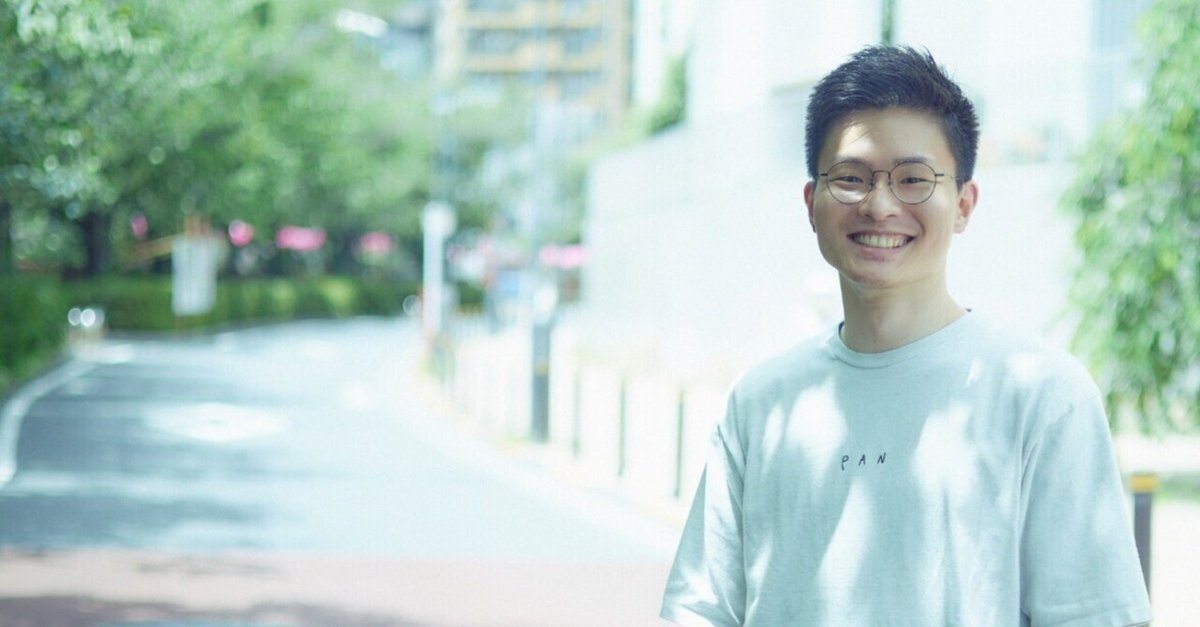
未分化な言語が教えてくれる、子どもたちに見えている世界。萩原広道氏インタビュー。
私たちが、普段何気なく使っている言語。言語を習得する以前、自分自身が物心つく前の世界がどのように見えていたのか、思い出せる人はほとんどいないと思う。
萩原広道氏は、子どもたちの発達を言語の側面から研究することで、子どもがどのように世界を捉えているのかを明らかにしようとしている。それは、私たち大人にとっても非常に多くのことを教えてくれる。

子どもたちに見えている世界。
-まずは、萩原さんの専門から教えてください。
萩原:子どもの発達が専門だということにしています。現在は、特に子どもの“ことばの発達”を中心に研究を進めています。
-具体的にはどのような研究なのですか?
萩原:子どもが話し始めると、「ワンワン」とか「ブーブー」といった単語を言えるようになりますよね。幼い子どもは、そういった言葉を大人が言うところの「犬」や「車」とは違うものとして捉えているのではないか、ということを大真面目に研究しています。
-子どもは大人とは違うものとして言葉を捉えているんですか!?不思議ですね…!
萩原:言語発達の過程で、子どもが分かるようになる言葉や言えるようになる言葉には、ある程度の順序性があることが知られています。例えば、「コップ」「クック」(靴)などの“モノの単語”は比較的早く覚えられることが分かっています。それに比べると「飲む」とか「履く」といった“行為の単語”は習得の難易度が高いんです。多くの子どもは、生後約半年ごろから少しずつ単語を理解し始めますが、1歳半から2歳くらいになると、モノの単語を中心に語彙をどんどん増やしていくといわれています。
-なるほど。
萩原:当然ですが、大人にとって、「コップ」や「靴」はモノの名前を意味しますよね。仮に靴に花を生けて花瓶として使っていたとしても、それは「靴」だと認識できます。でも、1歳半ごろの子どもたちにとっては、「靴」という単語はモノとしての靴だけではなく、「靴を履く」といったモノと行為とが渾然一体となった概念であることが私たちの研究から分かってきています。靴に関わる出来事がまるっとくっついた概念が「靴」の意味なんです。
-モノだけを分けて考えていないということですね。
萩原:モノの単語、いわゆる名詞のように見えたとしても、子どもたちにはモノにまつわる周辺の状況も“未分化な状態”として単語の意味に入り込んでしまうということです。私たち大人は当たり前だと思って「靴」という単語をモノの名前として使っていますが、同じ単語でも子どもたちには違うものとして捉えられているんです。つまり、子どもたちは、私たち大人とは世界の見え方が異なるんですよね。

-私たち大人の当たり前とは全く違うんですね。どのような研究方法でこういったことが分かるのですか?
萩原:私たちが実施した調査は次のような感じです。まず、お子さんの目の前に大きなモニターを提示して、左右で別々の動画を流します。片方には「ある人が靴を履いている」動画を流し、もう片方には「ある人が両手にカゴを持って、靴とは無関係な行為をしている」動画を流しました。その状態で「靴はどっち?」って質問をすると、1歳半くらいのお子さんでも「靴を履いている」方の動画を見たり指さしたりしてくれます。
-ある程度、「靴」という単語を理解できているんですね。
萩原:えぇ。ここで少し方法を変えてみました。例えば、モニターの片方には「靴を変なふうに使っている動画」を、もう一方には「カゴをあたかも靴であるかのように履いている」動画を流しました。モノと行為とがちぐはぐでマッチしていない動画のセットにしたんです。すると、先ほどは「靴」を理解していた1歳半の子どもたちが、「靴はどっち?」と聞かれてもどちらだか分からなくなってしまうんですね。答えが安定しなくなるんです。
-そうしていくと、「靴」をモノだけで認識しているわけでないことが分かってくるわけですね。
萩原:えぇ。ちなみに、2歳に近づくにつれて、「変な使い方をしていても靴は靴やん」ということが分かるようになっていきます。つまり、大人にとっての「靴」と同じ“モノの名前”に近づくわけです。今お話ししたのは調査のほんの一部で、実際には他の種類の動画セットも使いながら、お子さんが「モノの名前のようにみえる単語」をどのように理解しているかをより詳しく調べました。その結果、少なくとも1歳半ごろの子どもにとっては、「靴」のような単語は“モノの名前”ではなく、「履く」など“モノに特有な行為”の情報も分かち難く結びついた未分化な意味をもつことが示唆されました。これらの結果は、Cognitionという認知科学の国際誌に掲載されています。
-そういった研究を通して、社会に対してはどのような意義があるとお考えですか?
萩原:もちろん、子どものことばの発達を支えるためのより良い子育てや保育・教育・療育の在り方などを提案することに繋がるという意義もありますが、究極的には、子どもがどんな世界の中に生きているのか、世界をどんなふうに捉えているのか、その捉え方がどう変わっていくのかといった事柄を研究することで、人間の発達の謎を解き明かすことに貢献できると考えています。
-子どもが見ている世界を描くというのは、すごく素敵な研究ですね。
萩原:私たち大人にとっての当たり前と、子どもたちにとっての当たり前が違うということを実証的に解き明かすことは、実は一般社会における大人同士のコミュニケーションにも多くの示唆を与えてくれるのではないかと思っているんです。大人でも、他者が何を考えているのかって本当は分かりませんよね。でも大人は、状況に応じてある程度うまく“上辺のお付き合い”ができてしまいます。
-あぁ。なんかその場ではうまくいっているようでも、本当の意味でのコミュニケーションがうまくいってないことってありますよね。
萩原:子どもたちは、言葉だけでなく行動すらも未分化なところがあると思っています。思ったことが行動として出やすいとか。子どものふるまいには、他者と上手に繋がるためのヒントがたくさん隠れていると思うんですよね。

言語のない世界からある世界へ。
-萩原さんの研究結果は、日本の子どもたちの発達に限った話ではないんですよね?
萩原:私たちの調査そのものは日本のお子さんたちが対象でした。でも、英語やドイツ語など欧米の言語圏における発達研究でも、子どもの言語は未分化だと主張していた理論家もいます。1963年にウェルナーとカプランという研究者が『シンボルの形成』という書籍を出版しているのですが、その中で彼らは「子どもにとっての言語は、初期には未分化で文脈や状況に張り付いている。それが発達に伴って段々と分化し、複雑な発話ができるようになっていく」という旨の主張を展開しているんです。
-萩原さんの研究に近いですね。
萩原:そうなんです!『シンボルの形成』は半世紀以上も前の書籍で、子どもの行動を緻密に観察した数々の研究をベースに発達理論を構築しています。私たちの研究は、この理論で主張されていることを実証的なデータによって裏づけたものだともいえます。他の言語圏の子どもたちを対象にした調査にも今後挑戦したいと思っていますが、『シンボルの形成』の理論がいわゆる欧米圏の言語発達研究に依拠していることを考えると、言語や文化に関わらず、子どもたちにとっての世界の見え方や言語の捉え方は発達的に変化する、といえるのではないかと思います。
-そういった言語・文化圏によって、分化の過程は違うものなんですか?
萩原:言語や文化の違いによって、状況のどのような側面に注意を向けやすいかが異なるといった研究は進んでいますね。
-注意の向けやすさが異なる?
萩原:例えば、日本語では衣服を身に着けるとき、「着る」「履く」「被る」「かける」などいろんな動詞で表現しますよね。でも、英語だとこういう行為は「put on」とか「wear」といった動詞にまとめられてしまう。
-言われてみれば確かに…!
萩原:言語によって、行為をどのくらい細かく表現し分けるかが異なるんです。中国語の場合も、一般的に行為の言葉は細かく分化することが知られているんですが、こういう要因の影響か、英語圏の子どもたちは行為よりもモノの変化に注意を向けやすいのに対して、中国語圏の子どもたちは相対的にモノよりも行為の変化に注意を向けやすいという報告があります。また、英語には単数形や複数形があるので、モノが「数えられるかどうか」が単語を習得する上で重要になってきますが、日本語にはそういう区別の仕方はありませんよね。このように、言語によって世界の切り取り方は変わってくる。ただ、かといって日本の子どもたちがモノの可算・不可算にまったく無頓着かというとそういうわけでもないので、言語によって世界の見え方が変わっていくのだとしても、多くの言語圏に共通の発達の方向性というものもあるのだと思います。

-それにしても、私たち大人も、かつては子どもたちと同じ世界を見ていたんですよねぇ。
萩原:子どものときにどんなふうに世界を見ていたのか、大人になってしまうともう思い出せないので、なんだか物悲しい気もしますよね。でも一方で、大人になるにつれて複雑なことを考えたり表現したりできるようにもなるわけで、大人になるのも捨てたもんじゃないと思いますよ。こういうインタビューでの言語コミュニケーションだって、大人だからこそできるわけで(笑)。
-そう言われると、大人で良かったと思えます。
萩原:そういえば、言語発達の研究でよく「あの頃のままでいられたら」と大人が嘆きがちなトピックがあります。音の聞き分けです。例えば、英語のLとRの聞き分けって、日本の赤ちゃんでも生後半年過ぎくらいまでは英語圏の赤ちゃんと同じくらいできることが知られています。ところが、日本語の環境で育つと、1歳に近づくにつれてこの聞き分けの成績は下がっていきます。そういう話を聞くと、「英語の耳になれたかもしれないのに残念!」と思われるかもしれません。
-今まさに、あの頃の耳のままでいれたら…と思っています(笑)。
萩原:でも、L/Rの聞き分けができなくなっていくことって、日本語を習得する最適なルートでもあるんです。日本語の場合、LやRの発音は「ら行」の音だとまとめてしまって問題ないですよね。いちいち「この音はL/Rのどっちだろう…?」と考えていたら、日本語を覚えるのはむしろ大変になってしまう。L/Rの発音を区別せずにまとめてしまうことで、子どもたちは、生まれてきた日本語の環境にうまく適応していると考えることができます。こうした適応能力は、子どもたちがもっている素晴らしい能力のひとつだと思います。
-それにしても、言語習得から見えてくる子どもの発達ってすごくエキサイティングですね。
萩原:言語というのは他者と繋がったり、世界を捉えたりするための一つのチャンネルです。特に大人になるにつれて、コミュニケーションのかなり大きな部分は言語に支えられるようになっていきます。でも、最初から言語を理解したり話したりするわけではない。発達の過程で、子どもたちは「言語のない世界」から「言語のある世界」にやってくるわけです。
-言語がない世界からある世界へ…。改めて考えるとすごいことですね。
萩原:しかも、多くの子どもたちは、この大旅行をほんの数年で駆け抜けます。その分、発達的な変化を観察しやすい。それに加えて、変化の度合いは緩やかになったとしても、言語は生涯を通して習得されていくものでもあります。語彙は大人になっても増え続けるし、外国語習得だってあります。一生を通して発達していく対象なので、研究していて面白いです。私自身は、言語だけを専門に研究しているわけではないですが、それでも言語ってとても面白い媒体だと思います。
-ちなみに、一生を通して言葉は分化し続けるんですか?ある程度大人になると、分化が止まるんですか?
萩原:単語の習得に関していえば、果てしなく枝分かれしてどんどん細かくなっていく、というわけではないです。ある程度意味が分化したら、今度は“まとまる”という現象が見られるようになります
-まとまる?
萩原:例えば、コップ、お皿、グラス、スプーン…これらのモノは、「食器」としてまとめて呼ぶことができますよね。一度分化したモノの言葉が、別のレイヤーで統合されるんです。いろんな側面での分化と統合を行き来しながら、言語はさらに発達し続けます。

あたりまえは、それぞれに違う。
-そもそも萩原さんは、どうやってこういった研究アイディアを思いついたんですか?
萩原:私自身の経歴を辿りながらお話ししますね。高校生のとき、私は自分自身の可能性を狭めたくなくて、いろんな専門分野について学べそうな京都大学の総合人間学部に入学したんです。なんとなく「総合人間学」っていろんなことができそうだと思って(笑)。
-確かに(笑)。
萩原:でも、結局はある程度の学年になると心理学なり物理学なり…何かしらの専門分野を選ばないといけなくなってしまった。当たり前なんですけど。で、これは困ったと(笑)。
-結局どうされたんですか?
萩原:結局、専門分野は決まりませんでした。「総合人間学」なんてなかったんです。ただ、学問としての総合はできずとも、ひとりの人間をいろんな視点から見つめるというかたちでの総合人間学ならありうるんじゃないかと考えました。そして、そのイメージに一番近そうな作業療法学という分野を同じ大学のなかで運よく見つけて、思い切って転学部したんです。作業療法学は、生活上の障害をもつ人々の支援に携わるリハビリテーションの一分野です。この分野について学べば、人間を身体や認知・精神などさまざまな側面から探究できるんじゃないか、と期待したわけです。私なりの総合人間学が実践できるかもしれないと思ったんですね。
-あぁ。なるほど。
萩原:転学部してから、いわゆる発達障害のお子さんたちの発達支援に関わるようになったことが、今の研究に至る一番大きな転換点だったと思います。当時、学びの一環として、学生と現役のセラピストが一緒になってお子さんの発達支援に取り組むインフォーマルな勉強会に定期的に参加していました。彼らとやりとりを深めていく中で、子どもたちはどうやら私とは違う世界の捉え方や他者との関わり方をしているようだ、と実感したんです。それに気がつくと、もっと彼らのことを知りたいと思うようになりました。

萩原:その後、幼稚園や保育園・こども園で、障害の有無に関わらずいろんなお子さんと接する機会が増えたんですが、その中で今までの自分の常識が通用しないという体験をたくさんしました。例えば、2歳児クラスのお子さんが、紫色の絵の具の水が入ったペットボトルを「バナナジュースあげる」って私に渡してくれたんです(笑)。
-紫色のバナナジュースは斬新ですね(笑)。
萩原:大人だったら、紫色だから「ブドウジュース」だろうって連想しそうなものですよね。でも、その子はそういう世界の捉え方をしていない。子どもたちには、私とは全然違う世界が見えているかもしれないと思ったんです。
-同じものを見ていても、全然違うかも知れないと。
萩原:最近教えてもらった別のエピソードもあります。「歩くの疲れた」という子どもに対して「じゃあ走ろうか」って言ったら、走ったそうです(笑)。
-(笑)。
萩原:そもそも「疲れたから歩けない」という発想ではないということだと思います。あるいは、「疲れた」は大人にとっての「疲れた」とは違う意味をもっていて、「つまらない」「退屈」ということだったのかもしれません。子どもと大人とでは、常識が違うんです。
-大人からするととても不思議なことわりの中で生きているんですね。
萩原:子どもたちがどんなふうに世界を見ているかを研究することで、私も含めた大人がどのように発達してきたのか、その足跡をもう一度辿り直すことができるのではないか。そんな思いから、今の研究を始めました。そういう経緯を考慮すると、私は子どもたちの発達の中に、自分なりの総合人間学を見つけたのかもしれません(笑)。

イライラは、知らない世界の入口かもしれない。
-研究する中で、コミュニケーションについて子どもたちから学んだことってありますか?
萩原:「多分理解できないな」「理解されないな」という前提から考えるようにしています。理解したいと思ったなら、なおさら理解し合えないことの方が多いという前提に立つこと。子どもと関わる時に大事にしていることです。逆説的かもしれませんが、「分かり合えないよね」っていう前提の方が、うまくいくケースがたくさんあります。
-なるほど。
萩原:例えば、子どもと接していて、「なんでこんなこともできないの!」とイライラしてしまうことってありますよね。これは「こんなことできて当然」という前提があるからだと思うんです。自分にとっての「こんなこと」は他人にとっては「できないこと」かも知れない。
-そうか。知らないうちに自分ができることをベースに考えてしまっているんですね。
萩原:でも、日常の中で、こういうイライラするような相互理解が得られない状況は、実は自分の知らない世界を知るためのチャンスでもあると思うんですよね。そう考えてみんなが過ごせたら、世界は少しだけ優しくなるんじゃないでしょうか。もちろん、いつもそう上手くはいかないでしょうけれど。
-イライラしてしまうのは、子どもとのコミュニケーションに限ったことではありませんよね。
萩原:自分にとっての「当たり前」が他者とは違うと分かっていても、普段の生活の中では忘れてしまったり見過ごしてしまったりしますよね。前提を確認しなきゃいけなかったのに、そういったものをすっ飛ばしてしまったがために問題が起きてしまったということは、誰しも日常の中で経験していると思います。子どもという、大人にとっての“他者”を知る研究を通して、そういうことを丁寧にやっていくための心構えみたいなものを育むことに貢献できたらいいなぁと思います。

今この瞬間を楽しむための研究を。
-萩原さんは、これからどのような研究をしていくのでしょうか?
萩原:もちろん、一番関心があるのは「子どもの発達」という現象そのものですので、言語に限らずさまざまな側面から発達について調べていきたいと思っています。発達の研究をしていると、子育てや発達支援などを含んだ広い意味での教育という視点を要求されることもあります。成長や発達を促す方法について調べたり発信したりすることも期待されるんです。あえて例えるなら、アオムシがサナギになってチョウになるという過程を、どうやったらより効率よく早くできるかという視点に流されやすくなる場合もあります。
-「うちの子をちゃんと育てるにはどうしたらいいですか?」というのは求められそうですね。
萩原:実際に保護者の方からそういう相談を受けることもあります。もちろん、それはそれで重要な視点だし、場合によっては差し迫ったった問題かもしれない。でも、発達研究の役割はそういうことだけに留まらないと思うんです。私の研究には、人間が変化していく連続的な過程の中で、ある一コマを切り取ったときに、そこで何が起こっているのかを調べるような側面があります。私自身は、子どもたちが、ある瞬間、ある状態のとき、どういうふうに世界を見ているかを研究しています。子どもにとっての世界の見え方自体に興味があるんです。アオムシならアオムシのときにしか見えていない景色があって、その景色にはチョウから見た景色とは違った素晴らしさや尊さがある。そういう発達の一コマ一コマでしか見られない世界の面白さを描いていきたいですし、それを伝えていくことが、発達研究の大切な役割なんじゃないかと考えています。
-誰かのその瞬間をきちんと肯定してあげるような視点の研究なんですね。
萩原:良い/悪いは別として、生きている限り人間は絶えず変化します。大人になってもそうです。変わらない方が良いとまでは思いませんが、でも、今この瞬間、この場所にこうしていること自体を少しくらい楽しんでもいいんじゃないか、楽しむ余裕くらいはあってもいんじゃないかと思うんですね。そういう余裕があれば、自分以外の世界を知りたいと思えるかもしれないし、思わぬ方向に自分自身が変化していくかもしれない。
-そういうことを考えるためのヒントを子どもたちからもらえるというのは素晴らしいですね。
萩原:現実は憂鬱だし、未来には暗いことも多いですが、それでも、希望を失わずに次の世代に繋げられるような…未来への投資となるような研究を続けていきたいです。子どもたちから学んだことを、次の世代の子どもたちに返していくというか。何よりも、子どもに多少なりとも胸を張れる大人でいたいです(笑)。

これからの世界で失いたくないもの。
-では、最後の質問です。萩原さんがこの先の世界で失いたくないものはなんですか?
萩原:「違和感があったときに、それを面白がれるチカラ」ですかね。イラっとしたり不安になったり、解決しなきゃと焦ったりすることもあると思いますが、まずは素朴に面白がってみるというのが、コミュニケーションをスムーズにしてくれるかもしれないし、他者や自分を新たに発見することに繋がるかもしれません。そういった態度・心構えみたいなものを失わずにいたいなと思っています。
Less is More.
取材が終わった後、少し話している中で萩原氏が「すべての人が全部別々の生き物と思った方が良いかもしれないですよね。作業療法の実習中、ある先生に“スターウォーズみたいな世界を想像した方がいいと思う”って教えてもらったことがあります」とお話ししていたのが印象的だった。すべての人の前提が違うからこそ楽しく繋がれると、萩原氏の研究が教えてくれているような気がした。

(おわり)

